D’accord, Derrida: D’ailleurs, Derrida
「私の答えが私自身を明らかにするよりも、君の質問が君自身を表わしている」。
ミケランジェロ・アントニオーニ『さすらいの二人』
D’accord, Derrida.
現在が現在それ自身であるためには、ある間隔が、現在を現在でないものから分離するのでなければならない。しかし、現在を現在として構成することの間隔は、同じ理由で、現在を現在それ自体のなかで自ずと分割するのでなければならない。
(『余白』)
いつからそこにいたのかわからないままに、見られ続けられていると気がついたときには、決して交わらなかった視線として見る前に見ていたと認識する。それは現前と不在、すなわち見えるものと見えないものの境界に現われるハムレットの父親のような亡霊である。いるともいないとも言えない。不意にどこからかやってきて、どこかに回帰する一つのメタモルフォーゼであり、自己矛盾しながら、混乱させつつ、聞く人に語りかける不気味なものである。JDは、『マルクスの亡霊たち』において、そう語っている。だから、Jacques DerridaはJDと呼ばれるのにふさわしい。それはJe Déconstruisの頭文字にほかならない。
実際、名づけるという第一の暴力が行われたのである。(略)独自なものを体系のなかで思考し、それを体系に刻み込むこと、これが原ヱクリチュールの所作である。つまり、それが原暴力であり、固有なるものの、絶対的近接性の、自己現前の、喪失であり、実のところは決して起こらなかったことの喪失、決して与えられずにただ夢見られ、いつもすでに分割され、繰り返され、自己自身の消失においてしか出現することのできなかった自己現前の喪失なのだ。
(『グラマトロジーについて』)
おそらく亡霊は実体ではなく、熱力学の熱のような作用を意味するだろう。しかし、現代の亡霊は閉じられた系、平衡(Equipment)のシステムに働く作用ではない。それは開かれた系、非平衡(Non-equipment)のシステムでの作用である。それは熱力学第二法則、エントロピーにほかならない。今日の環境問題はこの不可逆的な散逸現象に起因する。二〇〇二年にスペイン沖で座礁して、重油を流出しながら、沈没したタンカーのプレステージ号は、その意味で、現代の幽霊船である。
この開かれた系は新たな歓待をもたらしている。JDによると、閉じられた系での伝統的な客人歓待はあくまでも主人の権限が絶対であり、客人はそれに従わなければならない。一方で、客を一切拒まない無条件の歓待も思い浮かべることもできる。と言うのも、開かれた系において、客は予測不可能に入ってくるからである。主人の権限が絶対的ではないため、客人との立場が逆転されることもありうる。両者の関係は決定不能になるというわけだ。無条件の歓待は、現実には、不可能であり、条件付きで客を歓待する。けれども、インターネットやEメールが普及し、多くの人がこうした歓待のアポリアに直面している。この二つの歓待が混在する決定不能な状態から歓待を考えなくてはならないとJDは主張する。伝統的な歓待には亡霊がつきまとっている。招き入れる家や集団の同一性を維持するために、亡霊のように、昔から守られてきたしきたりや掟、法がある。しかし、それは非平衡の系を平衡の系に強引に押しこめているにすぎない。予測不可能に訪れる客人が歓待の条件を流動的にし、新たな歓待の条件が顕在化してくる。
到来者にはウィ(oui)と言おうではありませんか、あらゆる限定以前に、あらゆる先取り以前に、あらゆる同定(identification)以前に。到来者が異邦人であろうとなかろうと、移民、招待者、不意の訪問者であろうとなかろうと、他国の市民であろうとなかろうと、人間、動物あるいは神的存在であろうとなかろうと、生者であろうと死者であろうと、男であろうと女であろうと、ウィと言おうではありませんか。
(『歓待について』)
二〇〇四年一〇月九日に亡くなったJDは今や亡霊である。その言説は見えるとも見えないとも言えない。JDをめぐる形而上学的言説に対して批判しつつ、JDの意義は存在論的な脱構築派の源泉という理解を決して許さない亡霊記述的な作業を通じて明らかになるだろう。
問いに、あらゆる問いに、応えることができずに、私はその代わりに自分自身に問う。応答することは可能だろうか、また、このような状況において、それは何を意味するだろうか、と。また、そして、応答可能性〔責任〕というものの定義に先立ち、私は、翻って、幾つかの問いを敢えて発する。しかし、それは応答可能性という概念を理論上仮定する〔担う〕行為ではないのか。それが既に責任をとることではないのか。他の人々に促すべきだとある人が信ずる責任のみならず、その人自身の責任を負うということでは?
(『貝殻の奥に潜む潮騒のように』)
JDの死因はすい臓癌(Le cancer du pancréas)と報道されている。すい臓は外分泌と内分泌を行っている臓器で、外分泌液には多数の酵素が含まれており、腸内に排出されて消化を助け、内分泌液はかのインスリンである。一九六八年に、ミネソタ大学医学部の外科医チームが死体の膵臓を使って四人の糖尿病患者にずい臓移植をしている。けれども、この臓器は移植が非常に難しく、仮に成功したとしても、生存率がいまだに低い。すい臓の病気はそれほど多くはないが、膵臓出血と急性膵炎は危険な病気であり、はやく治療しないと死ぬこともある。すい臓は「代補(Supplément)」が困難な臓器である。
「この『代補』の概念には、デリダの基本的な手つきが集約されている。デリダは主流・正常とされているあるシステム(デリダはむしろ「エコノミー」という言葉を好む)を、たんに『補う』ものとされる二次的なものに注目することから始める。そしてこの『補い』が、実は『本体』のシステム内部を侵食しており、その区別が決定不能であることを示す。この決定不可能性の場において、本体と補いとが逆転し、補いが本体に『置き換わる』のだ。デリダが見きわめようとするのは、代補というものではなく、むしろこの逆転という出来事である。この出来事において、正常でも異常でもない、新たな身ぶりや言語が発明されるからだ。この発明の際には、理想や目的など、外的な規範に頼ることもできなければ、たんに主流となるシステムを破壊することに、満足することもできない。それは外部と内部の境界にとどまり続けることによってのみ可能な、不可能な発明なのである」(林好雄=廣瀬浩司『デリダ』)。これは複雑でもないし、別に突飛な主張でもない。いかなる生物も他の生物や触媒と共生しなければ生きていけない。皮膚の表面や消化器官には無数の微生物が棲み、それによってヒトは生存している。そもそも共生とは寄生のことである。宿主にしても、微生物なしには生きていけない以上、宿主と寄生の区別は決定不能である。JDはそんな寄生という代補としてテクストを読解している。
テクストの外には何もない。そしてそれは、まずジャン=ジャックの生活が、あるいはママン、またはテレーズ自身の存在がわれわれにとって主たる関心事ではないからではなく、また彼らのいわゆる「現実の」存在に近づく手だてはただテクストだけからというわけでもないし、またこの限界を変更するいかなる手段もなければ、この限界を無視するいかなる権利もわれわれにはないからというわけでもない。(略)「危険な代補」という導きの意図をたどりながらわれわれが明らかにしようとしたのは、ルソーのテクストとして取り囲みうると信じられているものの彼方や背後にある、いわゆる「生身の」存在の現実生活のなかには、ヱクリチュール以外には何も存在していなかったということである。つまり、諸々の代補、代替的記号作用しかなかったのであり、こういうものは、差異的指示の連鎖のなかにのみ出現しえたのであり、「現実的なもの」は、痕跡や代補などの発動から意味をもつことによってはじめて付随発生し、付加されるのである。かくして無限に至るのだが、それは、絶対的現在、〈自然〉、「本当の母親」のたぐいの語群が名づけるものは、つねにすでにのがれ去っていて、一度も存在しなかったこと、意味と言語を開くものは、自然的厳然の消失としてのヱクリチュールであるということを、われわれがテクストの中に読み取ったからである。
(『グラマトロジーについて』)
すい臓(pancréas)は古典ギリシア語のpan(すべて)とkreas(肉)に由来する。色と触感が肉のようである点から、「全体が肉の臓器」としてつけられている。また、癌(cancer)はラテン語のcancer(蟹)に語源がある。乳癌で変形した乳房が蟹に似ているからである。すい臓癌(Le cancer du pancréas)はすべての-肉の-蟹を意味する。
でも、吾輩はヒトのように一生の論理ではなくて、種としての自然の論理で生きていくから、それほど心配していない。このあたりの海だって、昔は大陸と続いていた。そのころでも、御先祖様はどこかで生きていた。これからそのうち、海がまた干あがって大陸と島が続いても、吾輩の子孫はどこかで生き続けるだろう。海でなくて川や湖であろうと、水のあるかぎりカニの仲間は生き続ける。ヒトのように百年やそこらの短い時間でしかものを考えられぬようじゃ、カニの名がすたる。ところが、その長い年月に生物が死んだのがたまっていたのをヒトは石油と称して掘り出した。間もなく掘りつくすだろうとは言われているが、石油の利権をめぐってヒト同士で殺しあいをしているのが、あきれた話。そして、その石油を積んだ船がひっくりかえってヒトは大騒ぎをしている。吾輩が油くさくならないかなどと、つまらぬ心配をしているが、そんなことで味が変わったりするものか。いや、食われることなど考える必要はないのだが。海の底で暮らし続けるのだって大丈夫。干あがっても大丈夫と見得を切ったところだもの。それほどでなくとも、火山による溶岩の流入ぐらいのことは、今までもよくあった。海は、そんなやわなものじゃない。
もっとも、その石油を改修しようと、海岸を変えたりするのは、広い海に比べればたいしたことではないけれど、さしあたりは少し迷惑であるな。もともとが自然にたまっていた石油を無理に集めたのだから、それが海にぶちかまかれただけのこととは思うが、ヒトは今日明日の生活で生きる生物なので、海岸をいじりたがる。吾輩の側からすれば、これを機会にヒトが、百年ほど海から撤退してくれれば助かるのだが、ヒトの都合ではそうもいくまい。まあ、ヒトとカニは、おたがい食ったり食われたりする仲なのだから、あきらめてつきあっていくことにする。
ヒトのなかには、自然保護派というのがあって、ヒトがカニをいじめていると弾劾したりするが、そんなぐらいで負ける海じゃないからご安心を。それよりも、ヒトのほうがかよわいし、そのかよわいヒトが大きな海を守るつもりになっているのが滑稽。たまには吾輩のように、海の底から地球を眺めてごらんよ。あ、ヒトはそこ生きておれぬが、吾輩が食ってあげる。
(森毅『越前蟹はヒトを食う!?』)
見えるものと見えないものの境界からそれとして現われる亡霊の記述には、代補の観点から、JDが主演した映画を読解してみよう。エジプトのサファ・ファティ女性監督によるJDをめぐる五二分もしくは六八分のドキュメンタリー映画が一九九八年に公開されている。ジャン=リュック・ナンシーがわずかに出演している程度で、ほぼ全編JDのみ登場している。二〇〇二年にもドキュメンタリー映画”Derrida”(Directed by Kirby Dick & Amy Ziering Kofman)が公開されているが、JD以外に、妻マルグリットを含め多くの出演者がいるため、前作と比べて、話すことの差延、すなわち告げることによって自己が遅れて生まれる際限なく続く過程に欠ける。JDのテクストにおいて最初の主演映画は周辺に位置している。JDと映画の組合せは、それがポップ・カルチャーである点を除けば、意外ですらある。JDはほとんど映画について語っていない。JDは、不慣れなまま、まさに手探りで、この映画にとりくんでいる。その意味で、二作目よりも一作目の方が、作品の出来以前に、JDを考える際に、適当である。
女性の真理というものは存在しないが、それは、この真理からのそこ知れぬほど深い遠ざかり、この非-真理が、「真理」だからである。女性とはこの真理の非-真理性の名称である。
(『尖筆とエクリチュール』)
サファ・ファティは、二〇〇〇年にJDと共同で『言葉を撮る』という本を出版している。撮影はエリック・ギシャールとマルシァル・バロー、マリ・スパンセール、録音はジャン=フランソワ・マピールにヴェロニック・ブリュック、ステファヌ・ティエボ、編集はマリエル・イサルテルである。このロード・ムービーは日本では劇場公開はされず、短期間、各地のホールで上映されている。
映画のタイトルは『デリダ、異境から』である。原題は” D’ailleurs, Derrida”であり、英語では、”Derrida’s Elsewhere”である。それはラリー・ヴォシャウスキー監督の『マトリックス・レボリューションズ』に描かれたマトリックスでも、現実世界でもないトレインマンが支配する世界と言ってもいいだろう。フランス語の”d’ailleurs”は「だいたい」や「それに」にほぼ対応する日常的表現である。何か議論していて話題を変えたいときに、違う根拠で自説を正当化するために、使う。「俺は時間がないから映画には行けない。だいたい、金もない」というように、たんなる二項対立ではなく、他からの派生的な言説とである。言うまでもなく、撮っている方も撮られている方もマグレブ出身である以上、一種のオリエンタリズムとその脱構築も含んでいる。さらに、一九九二年に、エドゥアール・グリッサンらが組織してルイジアナで行われたシンポジウム「他所からのこだま(Echoes from Elsewhere/Renvois d’ailleurs)」も踏まえている。これは『たった一つの、私のものではない言葉─他者の単一言語使用』として一九九六年に発表されている。
I knew there’d be times like
this
When I’d sit at home and
reminisce
Oh how one’s memory slips...
So I close my book
And sighing, take a second look
Sure enough – I’m quite alone
Still, there no sound
So I spin-a-disc around and
around
And slide the needle in the
groove...
Drive down any highway baby
But don’t bid me adieu
Through a sea of twisting
byways
I’ll be trailing you
Eternity’ll solve our problem
Take it as you may
And destiny will stand
corrected
Should we connect some day
Another time - to spend
Another place - to go
Another love to share with you
Deep emotion springs from this
life
Wells up inside
Quick, pick me up and pour me
over
The clouds crying by
Another time - to spend
Another place - to go
Another love this time it’s
true
Anyway you want me lover
Used to be your tune
I looked you up - you looked me
over
My lucky strike won through
I was cut, dried and discarded
Just a rusty blade
But since I found my four leaf
clover
I’ve seen the light again
All the tears
In the world
Seem to fall from you
At their
Rainbow’s end
A halcyon day
Or two
How soon
We fool ourselves
How slow
We tread
Astral planes
Collide head on
And on and on we glide
As if forever
(Bryan Ferry “Another Time, Another Place”)
JDが地中海の海岸にたたずむシーンからこの映画は始まる。小柄で、白髪になり、少々腹が突き出しているものの、端正で上品そうな容貌のJDは「たった一つの、私のものではない言葉」、すなわちフランス語を口にしていく。マーティン・シーンに似た現代世界で最も著名な哲学者がそこにいる。
──さきほどアルジェリアのことをお話になりましたが、あなたにとってすべてはそこで始まったわけです……
──ああ、あなたは私にこんな風に言って欲しいのですね。「私‐は‐アルジェ‐近郊‐の‐エル=ビアール‐で‐同化した‐ユダヤ人の‐小‐ブルジョワ‐家庭‐に‐生まれ‐ました……」と。そんな必要があるんですか。うまくできそうにありません。手伝ってくださらなければ……。
(『中断符号』)
監督とスタッフだけで内戦中のアルジェリアへも撮影に渡っている。JD本人は行っていない。危険かどうか以前に、これだけの世界的な哲学者がアルジェリアを訪れたとなると、一九八一年のプラハ同様、いろいろと憶測が飛んでしまう。
je veux vivre, vivre
varenaich, enaich
je veux vivre pour manger touts
les livres
je veux vivre pour connaître
les enfants
de mes petits enfants, pour
atteindre 100 ans
pour atteindre 1000 ans, pour
être heureux et libre
je veux vivre pour courir sur
la grève
je veux vivre pour embrasser
mes rêves
pour embraser mes jours pour
connaître l’amour
et les heures qui enivrent, je
veux vivre
je veux vivre, vivre
varenaich, enaich
je veux vivre, vivre
varenaich, enaich
je veux vivre toutes les joies
de la terre
je veux vivre et parcourir les
mers
je veux vivre pour sonner la
planète
sans en laisser une miette, je
veux voir toutes les villes
plonger de toutes les îles que
leur ciel me délivre
je veux vivre, vivre
varenaich, enaich
je veux vivre pour avaler le
monde
je veux vivre de mondes qui
frissonnent
de milliers de pays de millions
de personnes
d’un milliard de récit, je veux
pouvoir les suivrent
je veux vivre sans jamais
m’assoupir
je veux vivre sans jamais me
trahir
pour que chaque saisons
recolores mes passions
pour dévorer le temps qui cesse
de me poursuivre
je veux vivre
varenaich
pour ce que lorsque la mort
viendra me faire, un sort
elle ne puisse jamais, jamais
déraciner tout ce que j’ai planté
tout ce que j’ai qui me fera
survivre
je veux vivre, vivre
varenaich, enaich
je veux vivre, vivre
varenaich, enaich
(Faudel ”Je Veux Vivre”)
JDはアルジェリアのアンミーヤを話すことはできない。と言うのも、マグレブ・フランス本国・ユダヤの記憶という三重の分離があるアルジェリアのユダヤ系家庭の生まれだからである。その痕跡は割礼としてJDの身体に刻まれている。
ある意味ですべてのテクストは自伝的であると私は確信しています。
(『肉声で』)
JDは自分のテクストが自伝的だと自覚している。特に、晩年になると、この映画も含めて、講演や書簡、対談、告白など一人称のテクストが主流になっている。JDは、『耳=自伝─ニーチェの教育、固有名の政治』や『盲者の記憶─自画像およびその他の廃墟』において、自伝は哲学者の生涯と作品の境界であって、内部でも外部でもなく、書くものの中に盲人としての自分自身の自画像を見出すと言っている。JDは、自らのテクストを通じて、盲者の亡霊の自伝を書いている。
JDのルックスに関して、長い間、読者は盲者であることを余儀なくされている。しかし、モーリス・ブランショのような顔のない作家でいる状態は、突如、暴力的に終わりを迎える。チェコスロバキアの迫害される知識人を支援するヤン・フス協会を設立したJDは、一九八一年一二月末プラハ空港の税関で、麻薬の製造および不法取引により当局から逮捕される。フランス政府の働きかけによって有罪ながら国外追放処分となり、釈放され、帰仏する列車の中で、JDはフランスのテレビ局により最初の映像が撮影される。それまで、JDは顔写真を公開していない。一九八四年、二度目の来日の際には、『朝日ジャーナル』五月号がJDのポートレートを表紙に採用している。JDは、ジャン=ポール・サルトル以来、最もポップ・カルチャーに影響を与えた哲学者として見られるようになっている。実際、何度かポップ・ミュージックでも歌われている。
フランスの風景の中に住んでいる者なら誰でも、私の世代の誰かがサルトルを無視したことはなく、サルトルをやり過ごしたことはないということを、よく知っています。そんなことは不可能なのです。
(『言葉にのって』)
パレスチナ問題やフランスの移民問題へのアンガジュマンもそうだが、JDの言葉が時代のモードになったというのはサルトルに匹敵する。「ディコンストラクション」は、八〇年代には、知的でちょっとオシャレな流行語となっている。流行は雪崩のような非線形現象であり、哲学は社会に対し力を発揮できる。JDは、現代思想最高のポップ・スターとして、その言動が世界的に影響を与えるようになっていく。
"My perfect reflection
swims through the drowning pool.
The sky is gone. My world is in
deconstruction"
The fallen that dreams suicide
Takes the needle, instead of
the gun
The victim who self crucifies
can't realize
Christ is a weapon that chisels
at our lives
Deconstruction
The martyr takes his aim and
wounds the holy man
And on the eighth day God made
the art of war
And laughing planned the end
Who will tend the garden when
the snake swallows the light?
Who will eat the decay when the
worms have lost their sight?
Who will rape the weak when
there's nothing left to gain?
Who will till the soil of these
barren black remains?
Deconstruction, deconstruction
Who will lick my wounds when
they take away my speech?
Will you stand in line while
the shepherd hunts his sheep?
Could you see tomorrow if I
took away your eyes?
Can you crawl from under new
age prophecy's despise?
Deconstruction, deconstruction
Deconstruct my reality and let
me slip away, I am the dog
Who will tend the garden when
the snake swallows the light?
Who will eat the decay when the
worms have lost their sight?
Who will rape the weak when
there's nothing left to gain?
Who will till the soil of these
barren black remains?
Deconstruction, deconstruction
Deconstruction, deconstruction
Our world is in deconstruction
Our world
(Nevermore “Deconstruction”)
JDは自分の思想が安易に分類されることに抵抗し、ポスト構造主義思想の一つとして流通した通説を後の著作では自らの思想を繰り返し定義し直す。それは自身の名声に対するパロディであり、JDをめぐる言説に対する脱構築の試みと言える。この映画もその一環であろう。
We talked up all night and came
to no conclusion
We started a fight that ended
in silent confusion
And as we sat stuck you could
hear the trash truck
Making its way through the
neighborhood
Picking up the thrown out different
from house to house
We get to decide what we think
is no good
We're sculpted from youth, the
chipping away makes me weary
And as for the truth it seems
like we just pick a theory
The one that justifies our
daily lives
And backs us with quiver and
arrows
To protect openings cause when
the warring begins
How quickly the wide open
narrows
Into the smallness of our
deconstruction of love
We thought it was changing, but
it never was
It's just the same as it ever
was
A family of foxes came to my
yard and dug in
I looked in a book to see what
this could possibly mean
Cause there is fate in the
breeze and signs in the trees
Possible tragic events
When forces collide with the
damage strewn wide
And holes blasted straight through
the fence
The sky starts to crash the
rain on the roof starts to drumming
And laid out like cash your
take on my list of shortcomings
The show starts to close, I
know how this goes
The plot a predictable showing
And though it seems grand it's
just one speck of sand
And back to the hourglass we're
going
Back to the smallness of our
deconstruction of love
We thought it was changing, but
it never was
Our deconstruction of love
(Indigo Girls “Deconstruction”)
知的でオシャレな戯れとして、拡散していき、時代になじみ、風景の一部になるとき、正統と異端の区別が決定不能になっていく。それは散種であり、JDの言説はつねに脱構築される。
私が難解だという非難は、基本的に誤っています。私より難解な哲学者は山ほどいますよ。それに、私がただ難解だとしたら、大したことではないでしょう。私を難解だと非難する人たちは、正確に読解の作業をしていないか、それとも、そのことが充分にわかっていながら初めからそれを拒絶した方がいいと考えているかです。私は、明快さによって事態の複雑さが損なわない限り、明快であるために私にできることは何でもしています。
(『言葉にのって』)
ハンフリー・ボガートのように、猫背で、JDは、ラップをBGMに、“HUMANITIES
OFFICE BUILDING”と読める建物の階段を上り、教室に入っていく。
This year the seminar consists in
analyzing in what way the Christian schemes are prevailing in the world. Beyond
the Christian cultures, even in
JDは言葉遊びがすぎると一部の哲学者からずいぶん非難されてきたが、それをラップと考えることもできるだろう。INTIKやMBS(Le Micro brise le silence)の先駆者として、JDをラップ哲学者と見ることは、決して悪くない。
学生たちに英語で語りかけるこのセミナーのシーンの直後、カメラはJDの自宅を訪れる。JDはテーブルでだけ仕事をすると説明する。そこは雑然として微妙にアナーキーで、散種という趣がある。
「散種(Dissémination)」は、ジル・ドゥルーズ=フェリックス・ガタリも「リゾーム」と植物に由来する比喩を使っていたように、最もポストモダン的状況を表現したキーワードの一つだろう。ポストモダンは、たとえ東浩記が「動物化するポストモダン」を正当化しようとも、植物化を意味する。散種は「意味の散乱」であり、たんなる多義性ではない。多義性は一=多の二項対立の圏内にある。『たった一つの、私のものでない言葉』で唯一性を強調しているように、新たな用語を提起する際、二項対立的な図式に舞い戻らないようにしなくてはならない。多義性では、テクストを読むとき、なぜその単語が使われたか知るために、社会的・時代的背景を考察する必要から、無限に遡れてしまう。しかし、それは過去の意味を解明することであり、過去は未来に回復させるために存在しているという目的論を正当化する。線形的な歴史観にすぎない。多義性は、結局、固定化されてしまえば、同一性と同じである。将来、今使われている言葉の用法もどうなるかわからないのであり、おそらくそれは一つの意味に回収されえないだろう、一般に多義性と呼ばれているものは可逆的な運動にすぎない。他方、JDの散種は不可逆的で不規則に拡散していく現象である。JDは文学的テクスト、特に詩にこうした現象を読むだけでなく、哲学的ヱクリチュールからも見出す。つまり、散種はエントロピー的な拡散の現象である、
目的論的総合化的弁証法は、たとえどれほど遠く離れた時点であろうとも、ある特定の時点で、テクストの全体性をそれの意味の真理へと再び取り集めることを可能にするはずである。(略)かくして当のテクスト的連鎖の開かれた産出的な位置ずらしは抹殺されてしまう。(略)散種はある還元不可能な生成的多様性を表わしている。
(『ポジシオン』)
カメラはJD愛用のPCを映し出す。それはMacPCである。これは意外ではない。IBMのPCにWindowsOS、あるいは自作のPCにLinuxOSでもなく、五月革命、六八年の思想家である以上、やはりApple社製を選ぶべきだろう。
JDは屋根裏部屋を本や資料を置く倉庫にしている。そこは「崇高」なる場所であるけれども、下の部屋のテーブルで執筆する。テクストを書くことは、そのため、上と下の融合による「昇華」の試みであるとJDは茶目っ気たっぷりに告げる。
プラトンの署名はいまだ完了していない。
(『他者の耳』)
JDの最大の意義は、JDが西洋形而上学という線形哲学に潜む非戦形成を顕在化させたことだろう。西洋形而上学は非線形を線形に還元して、統一性を考察する反面、線形的認識では把握できない物事、すなわち同一性に組みこめない事象は存在に値しない他なるものとして排除・抑圧してきた歴史を形成している。こうした「ロゴス中心主義(Logoscentrisme)」は論理・理性・秩序・進歩などを尊び、西洋はそれを支配的にして社会・文化・思想のあらゆる領域を構築している。主体や意識、実体といった伝統的哲学の中心概念はこの発想から生まれている。JDはこの現前主義の「脱構築(Déconstruction)」を提唱する。それは、既存の線形的な哲学的概念をただ否定するのではなく、この概念を使用しながら、形而上学が隠蔽・排除した非線形性を復権させようとする作業である。
哲学を「脱構築する」とは、哲学の諸概念の構造化された系譜学をそんなふうに最も忠実な、最も内的な仕方で、しかし同時にまた、哲学によって形容されえないような、名づけえないようなある外から出発して考えることであるでしょう。この歴史はあるものを包み隠し、ないしは禁止しえたのですが、そしてある個所で欲得ずくのそうした抑圧によってみずからを歴史たらしめたのですが、哲学を「脱構築する」とは、包み隠され、禁止されえたそういうあるものを、それと規定することでしょう。
(『ポジシオン』)
ジョナサン・カラーは、『ディコンストラクション』の中で、脱構築とクルト・ゲーデルの不完全性定理との類似性を指摘している。形而上学概念の二項対立に対して両者の境界が決定不可能であると証明し、テクストがある事柄を伝える内容として読めるとき、別のそれと矛盾することが中に含まれている読解はかの定理と酷似しているというわけだ。しかし、これは、柄谷行人を含め、広範囲に及ぶ影響を与えたものの、素朴なアナロジーである。無限をめぐる議論はプレ・ソクラテスのころから続いているとしても、必ずしも、一九二五年の定理がロゴスの正統性全般を脅かすことではない。脱構築をアリストテレス論理学への注釈から派生してきた数学基礎論と関連させるよりも、JDがプラトン以来の西洋形而上学批判を企てている姿勢を考慮すれば、線形性から非戦形性を表面化させた差分方程式とのアナロジーで考察する方が有効であろう。「二十世紀の数学は『集合」を基礎として成立している。それは、十九世紀の数学が、個物を対象とするより、その個物の含まれる集合を対象として、その集合性を論ずるようになったからである。だからそれが組織的に体系化された二十世紀の数学では、集合とその法則性が主調になる。それに伴って、集合それ自体の深い理論としての集合論が生まれる。こちらはまあ、職業的数学者の、そのまた一つのグループだけの話だが。ところで、二十世紀も後半では、集合より以上に、集合から集合への写像関係を重視する圏(カテゴリー)論的発想が強くなっている。それでも集合はあるのだが、限定的に純粋の集合ともなると、確定した標識の集合に使われるくらい。ここでも二つの使われ方があって、標識の集合からの写像として、個物がコード化される。逆に、標識の集合からの写像によって、個物がどの標識に帰属するかで分類される。なんとなく現代社会のメタファーのような気がしませんか」(森毅『「アジア」「外交」「集合」』)。
JDの脱構築は差分方程式を用いて線形に潜む非線形を顕在化させる試みと譬えることができる。規則が不規則を生み出すことをJDはテクスト読解を通じて明らかにする。こうした数学的事例の本格的な紹介は一九二〇年代に起きてはいない。JDが大学入学資格試験に失敗した一九四七年に、ジョン・フォン・ノイマンがスタンスロー・M・ウラムと共同で『確率論的過程と決定論的過程の結合について(On
Combination of Stochastic and Deterministic Processes)』において、素朴な線形の二次方程式を次のような差分方程式にすると、不規則に変動する時間波形を示し、非線形性質が表われると発表している。
f(x)=4x(1-x)
x(t+1)=4x(t)(1-x(t)), t=0,1,2,…
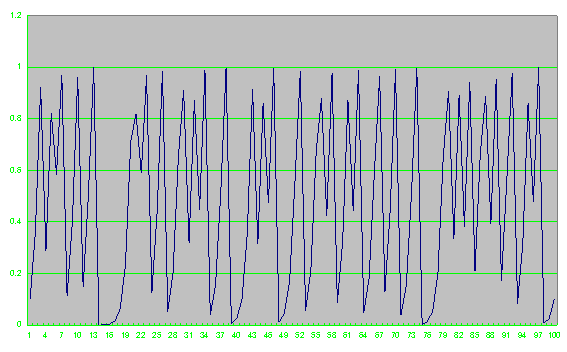
これは「ロジスティック写像(Logistic Map)」と呼ばれる。決定論であるとも、確率論とも言えない決定論的非周期性の動きを見せている。『有限責任会社』や『署名 出来事 コンテクスト』などでJDが言及している反復と変質を含む「反復可能性(Itérabité)」はこの決定論的非周期性の別名と理解できよう。不可能性の可能性がそれとして現われるというわけだ。JDは脱構築によって線形に潜む非線形を明らかにし、それがどこにでもあることを示す。そのため、線形からアプローチしなければならない。竹田青嗣は『〈差異〉と(根源)』においてJDがエドムント・フッサールよりも形而上学に後退していると批判している。しかし、それはフッサールの現象学が非線形現象の認識を探求しているのに対し、JDは線形と非線形の境界を線形の側から模索しているからである。フッサールは『幾何学の起源』の中で幾何学が「生活世界」からいかに生まれたかを論じている。幾何学はプラトンがイデア論を展開する際の最も重要な隠喩である。その起源を問うことはプラトン以来の哲学の根本を揺るがすことにつながる。「認識論的説明と歴史的ならびに精神科学的‐心理学的説明、認識論的起源と発生的起源とを原則的に分離する支配的ドグマは『歴史Historie』とか『歴史的説明』とか『発生』とかの概念が、例によって許しがたいほど制限されるのではないかぎり、根本的に倒錯しているのである。あるいはむしろ、最も深く本来的な歴史の問題をまさに隠しつづけるこのような制限が、根本的に倒錯しているのである」(フッサール『幾何学の起源』)。生活世界は近代科学が見出した線的な世界、すなわち「学的世界」に対語であり、非線形的世界である。JDは『幾何学の起源』に長大の序文をつけ、フランス語に翻訳している。それを踏まえつつ、JDは、フッサールと違い、非線形から線形がいかに誕生したのかではなく、線形に非線形がどう隠れているかを考察する。JDは言葉と意味が線形的に結びついているわけではなく、言語のうちに働いている意味に非線形的不規則さがあることを露わにし、線形と非線形の決定不能性を示す。JDは、以前の学者たちの著作を脱構築することによって、言語がつねに変化していると訴える。脱構築は、哲学を支配している明晰と一貫性という線形的な理想と哲学の所産が伴う欠陥とされてきた非線形性の間の緊張関係を白日の下にさらす。
JDの脱構築の差分法的特徴は、別の脱構築と比較してみると、より鮮明になる。JDの脱構築と並ぶ最も有名な造語の一つである「差延(a-différance)」は時間遅れ微分方程式(Delay-Differential Equation)とも呼ばれる差分微分方程式(Difference Differential
Equation)として考えるべきであろう。差延は差異と遅延の二つの意味を持ち、戯れとしての活動であると同時に、諸差異を産出する非‐単一的かつ非‐根源的な起源である。差分法は組合せ論(Combination Theory)における微分である。『読むことのアレゴリー』で「文学言語について何らかの理論家をはかる前に、人は読む行為の複雑さを意識しなければならない」」と言い、修辞性に焦点を当てるポール・ド・マンの脱構築は差分方程式ではなく、偏微分方程式(Partial Differential Equation)である。それは無数の変数を一つを除いて定数として扱う微分方程式の応用だ。流体や電磁場、重力場、一般相対性理論、量子力学などで用いられる。シュレディンガー波動方程式はその代表である。JDが書くから迫るのに対して、ド・マンは読む行為に着目するように、JDと逆の方面から線形に潜む非線形を導き出す。「一般に理解されていなければいないほど、またどうしても誤解されてしまったり、過度に単純化されてしまって、実際に詩ったものと反対のことを詩っているように考えられたりしていればいるものほどその詩人が実は現代性を持つ可能性が大きい」(ド・マン『死角と洞察』)。偏微分方程式として扱うことで解けていたものに対して、定数をパラメータに戻し、その不可能性、すなわち非線形を顕在化させるのが彼の脱構築である。「複雑系は一般に構成要素が多いため、複雑系をモデル化する方程式の変数が多数必要になる。すなわち、複雑系の研究は、多次元力学系をいかに記述するか(複雑系モデリング)が、重要課題となる」(合原一幸『カオス学入門』)。複雑系モデリングでは、両者の脱構築の違いは明瞭である。次の状態を決定する時間発展、ならびに要素がとり得る状態変数の値はいずれも連続的である。しかし、差分微分方程式系でその要素が空間的に離散的であるのに対し、偏微分方程式系においては流体のように連続的である。また、要素間に働く相互作用は前者が任意、すなわち戯れであるが、後者では局所的だ。JDの脱構築が、イェール学派のゴッドファーザーと比較して、恣意的とさえ言える言葉遊びを強調するのはこの二つの相違点として認められる。
語る際の意図が無条件に受け入れられることは、言語学ならびに精神分析の意義を考慮するなら、ありえない。その結果、一つのテクストにも多くの正当な解釈がありうることになる。なるほど、近代以前において、共同体は自身を維持していくイデオロギーがあり、それは伝えられるのではなく、確認されるために芸術が表現されている。作者の固有な意図が芸術を通じて受け手に伝えられるなどという発送はない。近代以前、イデオロギーと表現は分数的な線形性として結びついていると思われている。近代は共同体に代わり作者個人の意図が重視されるようになる。今度は小数的な線形として意図と表現がつながっていると考えられている。意図は欲望の別名である。資本主義の発達が欲望を解放しわが、現代社会では欲望がデフレを迎えている。欲望は誰かとの共同意識というイデオロギーを媒介する。けれども、表現したいという思いはもはや既存のイデオロギーと一致しない。原因と結果の線形的な因果関係は成り立たない。テクストから作者の意図を考察するというのは近代的な遠近法的倒錯にすぎない。テクストをめぐる線形的な意味の体系は素朴すぎて、もはや読解の前提になりえない。脱構築は非線形を顕在化させる試みであり、もちろん、それはJDやド・マンの方法に限定されるわけではない。
線形はLinearであり、非線形はNonlinearである。非平衡にしろ、非線形にしろ、ノンの自然科学的認識である。線形と非線形は数学上も、自然現象でも、対照的な傾向を示しているが、いずれも欠かすことができない。非線形は、文字通り、非-線形、線形ではないものである。数量的な構成や変化が加法性や比例関係に基づくものが線形のシステムであり、そうでないものが非線形に含める。前者は要素還元主義が可能だから、関数の変数に具体的な数値を代入して計算すると、関数の値が決まるため、線形代数や微積分など完成度が高い自然科学の理論的体系がある。要素間の関係が線形だと、それらの独立性といずうれも等しい関係があると考えられる。一方、非線形はその実在は感じられていたものの、数学的な解析が困難であり、コンピューターが開発された後、数値計算やシミュレーションを通じて研究が本格化している。非線形現象には、原則的に、微分方程式が十分に使えない。非線形の微分ならびに差分方程式のパンルベ性というのもあるから、すべてではない。相互作用が非線形だと、要素間で特定の関係が強くなり、全体が一つの秩序を持って自己組織化したり、逆に、不安定性が雪崩のように増幅されてしまう。自然界の現象のほとんどが非線形なだけでなく、ファッションの流行やバブル経済のような社会科学的現象も非線形に属している。哲学も例外ではない。
二十世紀数学文化のキーワードを一つ、と問われたならば、人によってさまざまの答え方があるだろうが、ぼくなら「線形」と答えたい。
二十世紀を展望するために、世紀半ばに身を移してみよう。ちょうどぼくが、旧制大学の数学科を卒業したころ。今では数学の現場から離れているぼくだが、半世紀というのは、ワープするにほどよい距離でもある。
数学も含めてだが、文化イデオロギーをあげると、世紀前半は形式主義だったし、世紀後半は構造主義だった。二十世紀は専門家の時代でもあったので、さまざまの分野が閉ざされがちで、それだけにかえって、そこを通底するイデオロギーを求める。そして、そのときの支配原理として線形構造があった。
リニアーというのは、線形と訳されたり、一次と訳されたりしてきた。一次関数のグラフの直線を連想する人もあろう。もっと一般的には、比例関係の原理と考えてよかろう。
人間にはとかく、物事を比例関係で見たがる癖がある。本来は乗除の世界で考えるべきものまで加減で考えたりする。(株価なんかでも、下げ率を見るべきなのに、下げ幅に目が移る)。こうした場合なら、対数によって乗除の世界を加減の世界に変換すれば、比例関係としての線形性が見えてくる。
もっと一般的には、スレスレに接する線形世界で考えることで線形性が使える。十七世紀に微分法が作られたころは、それを接線法と呼んでいた。そして、法則として微分方程式が定式化されることで、決定論的イデオロギーが科学のイメージを作った。初期状態によって、その後の結果が決定されるからである。
半世紀前でも、非線形微分方程式はあって、ときに数学の主流になじまぬ現象が見つかったりしていたが、スタンダードな線形を数学文化の主流とするなら、非線形はエスニック文化だった。「非線形数学は数学ではない」という人まであった。「わざわざ線形化して微分方程式にしたのに、それを非線形で扱うとはね」と、「線形化されたものの非線形」をやや自嘲的に語る、その分野の研究者もいた。ともかくも、扱いがたきエスニック、というのが半世紀前。
その後の半世紀の働きには、コンピューターの存在が大きい。数学者たちがコンピューターに接して、それまでには手のつけようがなかった非線形方程式をコンピューターにかけてみた。その結果、たとえばそりトンのような、新しい数学的現象が見つかり、新しい分野を開いた。これはスタンダードな数学文化のなかにあるし、やはり線形性が支配原理として生きているけれど。
二十一世紀を考えるときには、二十世紀のキーワードを裏がえしたくなるものだ。二十世紀のキーワードがナショナルならば、二十一世紀はグローバルであろうとか。あるいは、二十世紀のキーワードがエネルギーならば、二十一世紀はエントロピーであろうとか。それならはたして、二十世紀が線形ならば、二十一世紀は非線形の世紀になるであろうか。
二十世紀後半に、線形がスタンダードで、非線形がエスニックという文化イメージがゆらいだのはたしかである。それまでの数学文化の思いこみを変えることで。
数学では、ツルッとした世界(連続世界)に対して、ボツボツの世界(離散世界)があるわけだが、法則性はもっぱら連続世界で考えられてきた。式処理には、そのほうが扱いやすかったから。数処理もあったが、数値解析というのは、半世紀前には数学文化の辺境だった。ときに奇妙なことが起こっても、それは近似処理技術の失敗と思われていた。
当節風に言うなら、これはアナログとディジタルになるが、コンピューターはもちろんのことにディジタルである。コンピューターの発現は、アナログとディジタルの力関係を逆転させた。おそらく本来は、連続と離散は対等な世界として、相互を近似しあっているのだろう。連続世界の微分方程式にあたるものは離散世界の差分方程式であるが、非線形差分方程式がコンピューターで処理されることで、新しい数学増が生まれた。カオスが評判になったのは、その文化的衝撃による。
ある種の非線形差分方程式では、初期条件からは結果が予測不能なカオス現象が生まれる。それまでは、決定不能性は不安定と考えられていたが、カオスというのも一種の安定であった。決定不能な安定なのだ。
決定論に対しては、偶然論がある。二十世紀数学は、確立解析を発展させた。こちらは数学のスタンダードに属するが、確立微分方程式という言葉にぼくは、キッチリしたデタラメさといったニュアンスを感じてしまう。そこではスタンダードな数学文化だけに、いくらか問題があるにしても、それも線形性の支配と見られないでもない。
それに比べれば、非線形差分方程式のカオスでは、決定論のなかの偶然といったニュアンスを感じてしまう。決定論と偶然論は、はたして二者択一的なものなのか。決定論的文化としての科学文化をどのように考えたらよいのか。
時代の支配原理はアンチを含むのが常であって、二十世紀後半に、線形の対抗原理としての非線形が脚光を浴びたのは当然としても、そのことがただちに、二十一世紀の支配原理が非線形になることを意味するわけではない。せいぜい、二十世紀の支配原理である線形に対抗しただけであって、それが二十一世紀の数学文化を生みだすかどうかはわからない。
でもぼくとしては、非線形差分方程式というのが、ツルリとしないでザラザラして、非決定論でウジャウジャしているところに、自然のあり方のイメージを重ねてしまう。二十世紀があまりに人工的決定論に支配されすぎたゆえに。
(森毅『非線形の世紀?』)
映画を通じて、JDは喋り続ける。この姿はJDの読者にとって意表をつかれる。沈思黙考の哲学者ではない。哲学者に関するイメージへのジョークでさえある。一つの言葉を発し終える前に次の言葉が飛び出してきそうな勢いで喋りまくる。
撮影の間ずっと、私は私のことを何も知らない未知の観客に語りかけようとした。
(『デリダ、異境から』パンフレット)
JDはまるでウディ・アレンのように落ち着きなく喋り続ける。言葉と言葉は線形的な関係を結んではいない。非線形的な現象として言葉が口からついて出る。それは乱流である。JDへのイメージは決定論的非周期性を示しながら、変化する。
純粋な表出とは、内容が現前しているような言表に生気を与える意味作用の純粋な能動的志向(精神、プシュケー、生、意志)であるだろう。指標作用のみが自然と空間のなかで起こるのであるから、純粋な表出は自然の中にではなく意識に現前するのである。(略)そういう「外出」は指標のなかの自己現前の性を、事実上、追放する。これまで実質的に言語の全表面を包含してきた指標作用は、記号のなかで働いている死の過程であることを今やわれわれは知るのである。
(『声と現象』)
この映画は最初から困難に直面している。映画はラジオの延長線上にないからだ。ドキュメンタリー映画の制約を承知して、むしろ、記録映像や説明のナレーションを省くなどそれを推し進めることで、クロード・ランズマン監督の『SHOAH ショアー』は傑作となりえている。スティ−ヴン・スピルバーグ監督の『シンドラーのリスト』が線形代数的な連続的物語だとすると、『ショアー』は離散的である。ドキュメンタリー映画は描く対象も本質や実体ではなく、それを現象として扱わなければならない。”D’ailleurs, Derrida”は映画と言うより、それに比べると、テレビのドキュメンタリー番組に近い。しかし、多くのドキュメンタリー映画はそういった類のものかミュージック・クリップの域を出ない。テレビは隣の部屋にいても、音だけで話がわかるように番組をつくらなければいけないが、映画はそうはいかない。絵によって語る必要がある。ところが、JDは喋り続ける。JDの語りが中心とする以上、バスト・サイズが増えざるを得ない。「ニュースでもバラエティでもそうですが、基本となる画面のサイズは、人の喋りが聞き取りやすいバスト・サイズ、半身より少し詰まったサイズです。(略)このバスト・サイズで会話をするのはどういうときでしょうか。かなり接近しないとこのサイズにはなりません。恋人たちであればそれで長い時間を過ごせるでしょうが、ふつうこのサイズの距離で話をしていたら、すぐに息が詰まってきます。(略)しかしこのサイズは、音声を中心とした表現では、とにもかくにも言葉が欠かせなくなってきます。映っている以上はなにかを喋れと、見ている方もついついそんな気になります。身の回りでテレビのように喋り続ける人がいたら、あまり会いたくありません」。スティーヴン・ソダーバーグ監督の『セックスと嘘とビデオテープ』は撮る者と撮られる者の関係を決定不能に陥らせ、この奇妙な感覚を逆に利用している。JDの映画にはそんなシーンはない。「映像は『動き』を獲得したことで、そこに時間というものを持ち込むことになりましたが、ここには落とし穴がありました。映像は三次元の実像を、二次元の平面に移し替えたものです。動きは画像という平面に記録されていますから、実像がどのようなサイズの平面に切り取られたかによって、時間の感覚的な早さが変わってきます。同じ動くものでも、それを近くで見れば早いと感じ、遠くで見ればゆっくりと感じます。目の前で通りすぎて行く列車と、遠くを行くそれとはスピードの感覚が違います。もちろんこの場合には、音響ということも大いに関係してますが」(小栗康平『映画を見る眼』)。「映像は物事の外界をとらえるものです」。だが、このとまりようのないJDの喋りがJDの理論自身の脱構築へと間違いなく誘っている。「時制とは過去形、現在形、未来形などをいうものですが、映画にはこれがないということです。強いていえば、映画には現在形しかないということになるでしょうか。回想で過去が語られたり、未来を夢見たりする場面であっても、私たちはそれらを『今、そこで起きていること』として映像を見ます。映像は空間も時間も部分として切り取られていますから、その欠けた空間、時間は次のなにかと結び付きながら、たぶん、ある全体を回復しようとするのでしょう。映像の、この相互に干渉し合う性質から、いわば必然的に要請されているのがモンタージュである、むしろそう考えたほうがいいのかもしれません」。モンタージュは『弔鐘』や『郵便絵葉書』などJDのテクストにおいてしばしば見られ、映画としてJDのテクストを読む行為が待たれている。「私たちは見ることで、対象物との距離を測ります。レンズを被写体に向けることも同じ行為です。見ているものの距離の表現です。距離をおいて感じるものです。被写体の一つひとつを『存在』としてとらえれば、そこにはどうしても自他の距離が残ります。私たちはその距離の中で、自分と他者とを隔てていることについて、多くを感じ、考えもしているのではないでしょうか」。あくまでもこれはテレビではなく、映画でなければならない。映画が「間隔化」の実践であり、見えるものと見えないものの境界に現われるからだけではない。「国債映画祭に参加したりすると、たいした仕事もしているわけでもないのに、どうして映画ではこんなにもたくさんの世界の人たちと出会えるのだろうと、不思議に思ったりします。一本や二本で世界まで出て行くのですから、ほかのジャンルではありえないことです」(小栗康平『映画を見る眼』)。
目は見るためのものではなく、泣くためのものである。
(『盲者の記憶』)
これは、カルトという意味で代補の成功例であるけれども、映画自身への脱構築にはなりえていない。しかし、「言葉を撮る」試み自体アポリアである。「言葉があり、表情があり、風景があって、それらは映画の中でそれぞれの意味を伝えようとしますが、いつまでもその直接的な意味に溜まったままだとも思えません。背後にあるもの、隠されているものが、いずれ姿を変えてしまうものとして混じり合っていて、そのどれが、どういう状態が表層なのかは、じつははっきりしていないのではないでしょうか。音楽はそういう間から、聞こえてきます」。アポリアの経験は不可能性の可能性であり、それは寺山修司が呼ぶ「地平線」である。それを見ているにもかかわらず、決して到達できず、ただ他者からは私がそこに立っていると見える場所にほかならない。JDが脱構築の読解をする際に、否定語を多用して語る点を考慮すれば、小津安二郎の晩年の映画がそれに相当するだろう。「劇を発展させない、場を主体とする、会話を物語に従属させない、こうしたことが重なり合って、小津さんの映画の文体が作りあげられています」(小栗康平『映画を見る眼』)。
いわゆる「エクリチュールなき民族」とは、たんにある型のエクリチュールを欠いているにすぎない。
(『グラマトロジーについて』)
プラトンの『パイドロス』の中で、ソクラテスは、声で話される言葉が「正しきもの、美しきもの、善きものについての教えの言葉、学びのために語られる言葉、魂の中にほんとうの意味で書きこまれる言葉」であるのに対し、「書かれた言葉の中には、その主題が何であるにせよ、多分に慰みの要素が含まれて」いるので、「言葉というものは、ひとたび書きものにされると、どんな言葉でも、それを理解する人々のところであろうと、ぜんぜん不適当な人々のところであろうとおかまいなしに、転々とめぐり歩く。そして、ぜひ話しかけなければならない人々にだけ話しかけ、そうでない人々には黙っているということができない」と説いている。哲学はこれからその確実性を確保するために、現前性を特権化し、非‐現前的、すなわち差異や外部、記号、他者を排除していく。JDはプラトン以来の西洋形而上学においてヱクリチュールに対してパロールが優位であるから、それを転倒しなければならないと主張してはいない。ヱクリチュールとパロールの境界を問い直す。パロールとヱクリチュールの対立は、『プラトンのパルマケイアー』によれば、「プラトン哲学の主要な構造的対立のすべてと体系をなす」のであり、「二つの概念の境界において、哲学の創設を決定づける重要な哲学的決定のようなものがなされている」。プラトン以来の哲学はロゴスと音声の一体性、パロールの現前性を真理として、ヱクリチュールを抑圧している。ところが、パロールもまたヱクリチュール同様、差異を持った記号の体系であり、非‐現前的幸蔵を有している。パロールもまたもう一つのヱクリチュールにほかならない。そこでJDは「グラマトロジー(Grammatologie)」を提唱する。これは音声言語や文字言語以前に働いている差異を分節する作用である。理性=音声中心主義と結びつくあらゆる学問に向けられた脱構築である。この作業には終わりがない。グラマトロジー自身が権威的な学問にならないようにしなければならないからだ。グラマトロジーはパロール支配によって確定されてきた学問の境界を辿り続ける試みである。
ロゴスが無限であり自己現前的でありえ、自己触発として産み出されうるのは、ただ声を通してのみである。声とは、ある種の記号表現(signifiant)である。それに遡り主観は、主観が発すると同時に主観を触発しもするシニフィアンを、自己から受け取る事故へと取り込む。つまり主観は、それによいシニフィアンを主観以外のところから借りずにすむのである。かくのごときものが、少なくとも声の経験──あるいは意識──である。つまり〈自分が-語るのを-聞く〉経験である。
(『グラマトロジーについて』)
哲学は、その創設の際、パロールと手を組んで、ヱクリチュールを抑圧してきたが、これにはパロールの持つ線形がキーになっている。パロールは、ヱクリチュールと違い、線形数学に基礎づけられていることが西洋形而上学の前提である。意識が自分自身に対して透明に自己現前するのは「自分が話すのを聞く(s'entendre‐parler)」という円環に基づいているだけとJDはロゴス中心主義は音声中心主義だと批判している。古代ギリシアにおいて、音声は歌声を指す。西洋では、歴史的に声楽が重視され、中世のキリスト教教会に至っては、器楽音楽を卑しむべき世俗的なものと排除している。古典時代の人々にとって、声は音楽に基づいている。詩人を共和国から追放したプラトンだが、音楽を重要視している。音楽は数学、特に幾何学に根拠を持っているからだ。プラトンはイデア論を語るとき、しばしば幾何学を比喩にして説明知る。「古代ギリシャのムーシケーは、今日の音楽のみならず、舞踏、詩や劇といった文芸、さらには天文(および天文学)までも含む幅広い概念であったのである」(笠原潔『西洋音楽の歴史』)。ピタゴラス学派以来、協和音が整数比で著わさせるため、音楽は宇宙の調和を研究するにも欠かせない。古代ギリシアの市民の子弟にとって、ムーシケーを習得することは、体育と並んで、必須の教育である。また、音楽を音響の数比的研究と見なす考えは中世にも続いている。音楽(musica)は算術(arithmatica)・幾何学(geometria)・天文学(astronomia)が数学(mathimatica)の四科(quadrivitium)の一つに含まれ、文法(grammatica)・修辞学(rhetorica)・論理学(logica)が属する弁論術(eloquentia)の三学(trivium)と合わせて、七自由(septem artes liberales)を構成している。これらは職能から解放され、知識を求める当時の「自由人にふさわしい(liberalis)」必須の教養であり、この基礎を見につけた後、哲学(philosophia)、さらに神学(theodocia)の研究へと向かっていく。古典ギリシア語は、現在のインド=ヨーロッパ語の多くと違い、ストレス・アクセントではなく、ピッチ・アクセントである。発話に母音の長短によるリズムを持ち、高低の変化がある。「ホメーロス」を例にとると、「ホ」にアクセントがあり、他の音にはアクセントがなく、その高低差はほぼ五度である。五度と言うのは、C音に対するG音のような関係がそれにあたる。この特性上、作詞は作曲と同一になり、演劇は、悲劇であろうと、喜劇であろうと、音楽劇である。音声は音楽であり、数学にほかならない。その意味で、音声はロゴスである。中世においても、器楽は教会から追放されているが、声によって聖なる言葉で神を讃える聖歌こそふさわしい。けれども、古典時代と違い、このころ、調律の矛盾が表面化している。音は、周波数を二倍にすると、オクターブが一つ上がる。オクターブの音程差を持つ低い音と高い音の周波数比は一対二である。純正完全五度の音程を構成する二つの音の周波数比は二対三であり、同様に、純正完全四度における振動比は三対四、純正長三度が四対五、純正短三度では五対六である。ところが、この比を用いて音階上の音を得ていっても、澄んだ唸りのない純正音響の整数比の音律が完全には成立しない。このピタゴラス・コンマやシントニック・コンマといった音律の問題点はキーが整数有限で、演奏中に音程変更が困難である鍵盤楽器において顕著になる。そのため、鍵盤楽器の調律から生じるウルフ音を発する誤差は、中世・ルネサンスを通して、特定の音に押しこめ、それを用いないことで対処している。それは呪われた悪魔の和音というわけだ。次第に、転調や新たな和音が考案されていくにつれ、その調律では十分に対応できなくなり、近代になると、平均律が採用されるようになる。「完全平均律では、完全五度の音程のみならず、長三度の音程も純正音程とならないため、中全音律や不等分律の醸し出す純正な響きなど求むべくもない。しかし、フェルト製のハンマーを持ったピアノが普及し始めた十九世紀の半ば以降の時代にあっては、その点はあまり問題にならなかった。フェルト製ハンマーのピアノの場合、そもそも音がクリアーでないからである」(笠原潔『西洋音楽の歴史』)。近代のロゴスは平均律に基づいている。ただし、基本ピッチが高くなると音の輝きが増すため、バイオリンなどの弦楽器は平均律より高めに調律する。音声はこうした矛盾を隠蔽してその調和を主張してききている。平均律の登場には、近代が分数ではなく、小数を中心にして扱う転換が関係している。「もっとも、分数の乗除情計算というのが、ちょっと矛盾した概念である。もともと、乗除計算をするのが面倒くさいので、分数を使うのだ。それも1から9ぐらいの、一桁の数字だけですまそうとする。高校あたりの公式で出てくる分数はそんなもの。計算しないために分数はある。それで、近代は小数になった」(森毅『「株価」「パチンコ」「分数」』)。音声=音楽は線形数学に基盤を持っているから、ロゴスとしての地位を確立してきたのであり、その体制を維持するために、線形数学を矛盾を解消するように、あわせていかなければならない。
私が強調するのは、人々が批判からまぬかれさせようとするまさにそのものを「教え込む」のは、つねに自然的なものを強調することによって、教育の内容あるいは諸形式を自然的なものにすることによってである、ということだ。(略)年齢を引き下げることと哲学教育を拡大することと要求することによって、次のことを理解させることができる(別にそういうことを望むわけではないが、反対者はそのことを理解させるのに努力するであろう)。すなわち、ひとたび諸々の偏見と諸々の「イデオロギー」とを消し去ってしまったなら、つねにすでに哲学する準備ができ、生来哲学することのできる「子供」というものをさらけだすことになるだろう、と。今日最も「秩序破壊的」と見なされている諸言説でさえも、決してこのような自然主義をまぬかれてはいないのである。それらの言説は、野生的な欲望へ、抑圧の単純な解除へ、束縛を解かれたエネルギーへ、もしくは一次過程へ何らか回帰することにつねに訴えているのである。
(『ヘーゲルの時代』))
フェルディナン・ド・ソシュールは、『一般言語学』の中で、ヱクリチュールと変わらないパロールの記号性を明らかにしている。「シニフィアン(signifiant)」、すなわち記号表現・意味するものと「シニフィエ(signifié)」、すなわち記号内容・意味されるものを規定し、シニフィアンとシニフィエが一体となったものを「シーニュ(sign)」、すなわち記号だと言っている。「言語には消極的な差異しかない」(ソシュール『一般言語学講義』)。シニフィアンとは言語が持つ実体のことであり、「言葉」という文字やその発音がシニフィアンであって、シニフィアンによって規定されたり、表わされたりする「言葉」に対するイメージ・概念がシニフィエである。JDは、ソシュールの功績を認めながらも、それではまだ不十分であると指摘する。このスイスの偉大な言語学者はパロールに潜む非線形性に触れながら、線形数学で把握しようとしているからだ。JDによれば、シニフィアンとシニフィエの関係が非線形にあり、その区別は厳密には不可能であり、それらが「差延」を起こすことで新しい状態を生じさせる。これはチェコのマルタ・グビジョヴァ(Marta Kubišová)がザ・ビートルズの”Hey
Jude”を聞いて、まったく違った曲”Hej, Jude”をつくり、ビロード革命のテーマ・ソングになっている。C’est une révolte? Non; c’est
une révolution.言語の体系には差分微分方程式が働いている。パロールであろうとエクリチュールであろうと同様である。
理性に対する革命は、それが表明されるや否や、理性の内部においてしか効果をもたらしえない。
(『エクリチュールと差異』)
しかも、音声自身も線形数学に基づいて把握されてきたが、呼吸運動をエネルギーとする非平衡散逸系である。それは非線形に属している。JDがこうした数学の変化を承知していたわけではなく、それと平行してテクスト読解において具現化している。
クラス分けされた固有なものを差異の戯れのなかに抹消することであるヱクリチュールは、それ自体、根源的暴力だからだ。
(『グラマトロジーについて』)
古典時代と近代は必ずしも連続していないけれども、線形という点においては一貫している。ロゴスは線形数学を意味しており、形而上学は非線形を排除する歴史である。フリードリヒ・ニーチェやエドムント・フッサール、マルティン・ハイデガーらは要素還元主義に代わる新たな認識を探求している。数学の危機はヒルベルト・プログラムの破綻ではなく、非線形の表面化である。一八九〇年代、ジュール・アンリ・ポアンカレは三体問題の研究を通じてカオスに辿り着いている。古代ギリシア以来、線形の秩序に支配されたコスモス=アポロが隠蔽してきた非線形的なカオス=ディオニュソスが、一九世紀後半から二〇世紀初頭にかけて、姿を見せてくる。けれども、JDは非線形へは足を踏み入れない。非線形をいかに把握するかではなく、線形と見なされていたものに潜む非線形を明らかにするのが目標だからである。JDは差分方程式を使い、言葉と意味の関係に隠れている非線形性を顕在化させる。ところが、伝統的な読解方法が線形を自明にてきたのであって、言語が思想を線形的に表現しているとか著者がテクストの意味の源泉だとかを前提にし、テクストに不変の統一的な意味があると信じている。JDはエドムント・フッサールの現象学とマルティン・ハイデガーの存在論に強い影響を受けているけれども、それを批判的に継承したと見るのは疑問である。JDは彼らとは別の哲学をそこからインスパイアしたと考えた方がいいだろう。それはテクストの本質や実体を明らかにするのではなく、レトリックに着目して、テクストを現象として扱い、言葉遊びに戯れ、読解自身も現象化させる試みである。JDはいかなる領域を扱っても、決定不能性にとどまり続ける点で最も二〇世紀を理理解していた哲学者だとも言える。それは西洋形而上学を否定ではない。非線形数学が線形数学を省みて発展し、線形自身依然として人類にとって重要であるように、蓄積されてきたその意義を認めつつ、隠蔽されてきた非戦形性を顕在化させただけである。JDは哲学的言説がより線形性に支配されている現状を考慮し、哲学の側から文学との境界を探り出す。哲学や文学の領域を自明視していないと同時に、文学を哲学の上位に置くというヒエラルキーの構築を企ててもいない。JDにとって重要なのはその境界であって、領域ではない。「コントロールのよいピッチャーというのは、いつも直球ドマンナカに投げるのではない。ストライクの枠すれすれに投げるのが、いいコントロールというものだ」(森毅『枠のあしらい方』)。
私は哲学的言説の境界にとどまろうとしています。
(『ポジシオン』)
JDのテクスト読解は、この戦略上、あるテクストの寄生とならざるを得ない。それは代補の読解だと言える。結果ではなく、過程の読解である。決定不能にとどまるためであり、弁証法的に止揚されず、自分自身さえも固定化させないように、際限なく続く。何か結論を導き出すのではなく、差延を浮き彫りにし、戯れる。
JDは、非線形現象として読解するテクストが差出人も宛先もない手紙だと指摘するが、これは線形的と見られていた写像が差分方程式によって非線形を示すことの比喩である。差出人の集合と宛名の集合は線的に対応する手紙が従来の読解だというわけだ。
あなたがたはこれら発送されたものを、私がかつて書いたことのないある本の序文として読むこともできるだろう。
その本が論じるのは、諸種の郵便、つまりあらゆる様式における郵便から精神分析に至るものであっただろう。
その目指すところは、郵便的効果について一種の精神分析を試みるというよりはむしろ、フロイト的精神分析という一つの特異な出来事から郵便物のある歴史およびそれについてのテクノロジーへと送り返すことにあっただろう。言いかえれば、発送についての、そしてまたなんらかの遠距離通信によっておのれを差し向けると称するすべてのものについての、ある全般的な理論へと送り返すことに。
(『郵便絵葉書』)
さらに、この非線形の書簡は新たな数値計算も要請する。中国人郵便配達問題に対応するには、NP完全問題同様、非線形変換を用いた量子アルゴリズムがその一つの手段として必要だからである。
この線形に潜む非線形を顕在化させる戦略に基づいて、JDは数々の概念を生み出していく。「痕跡」や「間隔」、「代補」、「散種」、「起源」、「グラマトロジー」、「耳伝」、「反復可能性」、「友愛」、「アポリア」、「亡霊学」、「歓待」、「赦し」などいずれも非線形へのキーである。それは狭義のテクスト読解にとどまらず、加齢と共に、JDはアンガジュマンにも適用するようになる。
われわれの言説は変更不可能な状態で形而上学的諸対立の体系に属している。この帰属幸蔵との絶縁は、次のものによってのみはじめて告知される。つまり、形而上学的諸対立の領野の内部にあって、その領野特有の戦略を自らにそむかせるようにその領野の力を利用し、全体系に波及するような関節はずしの力を産み出し、その体系のあらゆる方向に裂け目を入れ、徹底的に境界をぐらつかせる(delimit)ような、ある機構、ある戦術的な配備によって。
(『ヱクリチュールと差異』)
JDは、フィルムの後半、エル・グレコの絵画やロマニとの友愛について語る。エル・グレコの『オルガス伯の埋葬』は、JDにとって、重要なのは、危篤の母の誕生の記念日にスペインのトレドで出会ったからである。この絵画は『割礼告白』でも言及されている。お母さん子だったJDは、子供のとき、甘えん坊の泣き虫であり、怖がりで、幼稚園をいつも何とかサボれないかって考えて、仮病まで使っている。それはカール・ヤスパースに似ている。
このような非自己固有化(dépropriation)は、それについてニーチェがその真のな、その<正しい名>は友愛だと結論づけている。この別の<愛>の方へと、たぶんを合図を送るだろう。この友愛とは一種の愛である。だがそれは、愛よりもいっそう愛する愛なのである。それゆえこれらの名のすべてを代える必要があるだろう。
(『この狂った<真実>−友愛という正しき名』)
一九八一年に妻マルグリットの出身地であるチェコを訪れ、収監された監獄で、JDはロマニと出会うことで、友愛を発見する。それは非線形的な対他関係であり、悲惨な境遇の共有でもある。
Ay niña
Yo te encuentro
Solita por la calle
Yo me siento ay 'namorao
Yo me siento ay triste y solo
Djobi Djoba
Cada dia te quiero ma'
Djobi Djobi, Djobi Djoba
Cada dia yo te quiero ma'
Djobi Djobi, Djobi Djoba
Cada dia yo te quiero ma'
Pero me importa
Que la distancia hoy
Ya no nos separe
Yo me contento me de ti
Que no me diga
ay Paragua'ya ya yay...
Djobi Djoba
Cada dia yo te quiero ma'
Djobi Djobi, Djobi Djoba
Cada dia yo te quiero ma'
Djobi Djobi, Djobi Djoba
Cada dia yo te quiero ma'
(Gipsy Kings “Djobi, Djoba”)
映画として見ているのは撮られたフィルムの一部にすぎない。倉庫に書かれることのない割礼論に関する資料を集めているJDにふさわしい状況だ。ロラン・バルトは映画に出演した差、セリフが覚えられず、苦労したらしい。JDはよどみなく喋り続けるものの、ロバート・ロドリゲス監督の『フロム・ダスク・ティル・ドーン』に出演するクエンティン・タランティーノのごとく、不自然なカメラ目線を時々見せる。カメラにある程度慣れていないと、撮影にならないが、習慣化しては素人俳優の利点を生かせなくなってしまう。「演技経験のない人が映画に出ると、自分が見せる立場に立っているという自覚より、自分が見られているという羞恥心の方が強いでしょうから、技術としてハードルをどう越えて行くというかという発想をもちません。それに代わって、ふだんは意識していないけれど、その人に備わっている生活感覚、自然観といった、根太いなにものかがそこで手探りされていくように思えます。しかしこの道は、一度や二度は通れるけれど、手探りしないで通れるようになってしまうと、上手くいかないことが多くなるようです。芝居を繰り返していくと、どうしても言葉や、そこで相手にしている人間を対象としているからでしょうか、芝居が小さくなっていきます。プロットを運ぶことばかり考えて、芝居が現象的になりがちです。ハードルが芸を競うものに変わってしまいます。映画の形式が強くはたらくところでは、俳優の演技は完結的である必要はありません。むしろ未完のまま、理由づけされないまま、存在としての幅を広げてくれることを演出家は望むのですが、どうしても自分が『わかっているところ』でやりたくなってしまうのです。これは演出の側にもいえることですが、自分の手からなにものかを手離す、その手の離し方が難しいのです」(小栗康平『映画を見る眼』)。自分がたいした主張があるふりをして本を刊行しているとか目立っていることをすまなそうに喋り続けるJDは、見る者に、「未完のまま、理由づけされないまま、存在としての幅を広げてくれる」ている。
作家は、一つの言語のなかで、また一つの論理のなかで書くのであるが、その言語や論理の固有の体系、法則、生命を彼の言説は定義上完全に支配することはできない。彼はただある仕方で、またある点まで、自分が体系に支配されるにまかせながら、それらを用いているにすぎない。そしてつねに読解は、作家が用いる言語の諸形態のうち、彼が支配しているものと彼が支配していないものとの間の、作家当人によっても気づかされていないある関係にねらいを定めなくてはならない。
(『グラマトロジーについて』)
JDは、映画を通じて、奇跡的な年の一九六七年、『声と現象』や『エクリチュールと差異』、『グラマトロジーについて』を刊行した時期から、『割礼告白』、『アポリア』、『歓待について』、『言葉にのって』という最近の著作に至る自分の思考が、同一性の喪失や異質なものへの関心に特徴づけられていて、ここのところ使っている「秘密」や「割礼」、「赦し」、「責任」、「歓待」、「亡霊」といったキーワードも関連していると訴えている。それ以上に、猫のルクレティウスの墓などとりとめのない話がこの映画においては脱構築的である。 「原子は自身の有する重量により、空間を下方に向かって一直線に進むが、その進んでいる時に、全く不定な時に、又不定な位置で、進路を少しそれ、運動に変化を来らすと云える位なそれ方をする…若し原子がよく斜に進路をそれがちだということがないとしたならば、すべての原子は雨の水滴のように、深い空間の中を下方へ落下して行くばかりで、原子相互間に衝突は全然起ることなく、何らの打撃も生ずることがないであろう。かくては、自然は決して、何物をも生み出すことはなかったであろう」(ルクレティウス『物の本質について』)。
「ヱクリチュールの主体」はないなどと、私は一度も言ったことはありません。
(『ポジシオン』)
「私はここにこうする、『私は署名する』と」。そう告げた後、この映画は終わる。しかし、その署名は線形的に見えて、非線形的行為である。
祭りそのものが近親相姦そのものであるだろう、もし何かそのようなものが──そのものが──起こりうると掏れば。もし、起こるということによって近親相姦が禁止を強めることにならなければ。なぜなら、禁止以前には、それは近親相姦ではないからだ。禁止されると、それはその禁止の認知を経ぬかぎり近親相姦とはなりえないからだ。われわれはつねに、祭りや社会の起源の境界の手前か後方にいるのであり、またそこにおいては禁止が違反と同時に与えられる(であろう)ような現在に手前か後方にいるのである。……
それゆえ、この社会の誕生は一つの推移ではなく、一つの点、一つの純粋で虚構的でかつ不安定で、把握しがたい境界である。人はそこに達する時にそこを飛び越える。そこで社会は穿たれ、自己からの遅延が始まる。
(『グラマトロジーについて』)
近代国家の起源は独立宣言や人権宣言などの「書名」に基づいているが、JDは、『法の力』において、署名の問題から近代の政治的・経済的共同体を検討している。JDの説明はかつての現象学批判の展開と同じである。署名が署名者を創出するのであり、署名者は書名に対して贈れて出現する。署名が過去に素行しつつ、その起源を形成し、亡霊的な来るべき未来を生起させる。起源は虚構であるとも、実在であるとも言えない。署名者が主体として署名するという線形的な認識は、著名を脱構築すると、隠蔽されていたものが露わになる。署名はカオス現象における初期値である。JDは線形としての主体を脱構築することを通じて、非線形の主体を顕在化させる。主体を否定したのではない。署名がもたらす現象は、署名という初期値に敏感性を持っているため、主体が決定不能性に置かれている。近代的主体に代わって伝統的な共同体、閉じられた系の権威が強化されることがJDの理論から導かれはしない。署名の脱構築を通じて、私と他者を隔てる間隔化や自我と他我を分かつ差延に先立つ主体の存在を否定すると同時に、何ものかをそこに想定することも拒否して、その境界にとどまる必要性が明白になる。署名から生じる正義は、その非線形を自覚することにおいて、認められうる。
二重の、精密に階層化された、位置のずれた、また位置をずらすような、ヱクリチュールによって、高位にあるものを引き下げる反転と、ある新しい「概念」、もはや以前の体制のなかには内包されえない、また決して内包されえなかった概念の、侵入的浮上、この両者の間の隔たりを示さなくてはならない。この隔たり、この二面あるいは二局面は、分岐したエクリチュールのなかにしか書き込まれえないのであれば(略)、この隔たりは、寄せ集められたテクスト的視野と私なら呼ぶであろうものにおいてしか示されえないのである。
(『ポジシオン』)
この映画は九・一一の前に撮影されている。まだ起こりえぬあの出来事について、ここで、JDは暗示もしていない。これは九・一一の黙示録ではない。すでにJDは、『信仰と知』において、今日の宗教がたんなる伝統回帰ではく、科学技術と結びついているので、近代科学に宗教は「免疫」を持っていると指摘し、メシア主義に立脚することの危険性を批判している。メシア主義は歴史を超えた掲示に基づき、救世主や最後の審判などの到来の予測に支えられている。しかし、重要なのは、閉じられた系である宗教ではなく、何ものの到来を予測していない開かれた系の「信」である。それが他者との倫理的関係の基板になる。宗教以前の「信」である「メシア主義なきメシア性」は、地平線に「起源」を持つ。そうした「メシア主義なきメシア性」が無条件的な歓待へのきっかけになりうる。
九月一一日という日付は、次のことをニューヨークやワシントンで私たちへ予告したというよりも、むしろ思い起こさせるものでした。すなわち、これまで述べてきたことへの諸々の責任が、これほど特異で、先鋭的になったこと、必要となったことはないのだ、と。従来とは異なるヨーロッパの思想が、今日ほど急務となったことはありますまい。醒め、目覚め、覚醒=監視する脱構築的な批判が、ここで参加を要請=アンガジェされるのです。それはまた、政治家のレトリックや、メディアと電気通信技術の権力、自発的あるいは組織的な世論動向にあって、特に正統で揺るぎない真実と目されている戦略を通して、形而上学、資本主義的投機、宗教的、ナショナリズム的な心情の倒錯、主権主義幻想へと政治を癒着させるあらゆるものに対して、ヨーロッパの外で、ヨーロッパの内で、ありとあらゆる縁で、注意を怠らない批判です。早口で言わざるを得ませんが、断固として言わせていただきます、ありとあらゆる縁で、です。 9月11日の犠牲者全員に対し私は絶対的な同情を表明するものですが、それでも言わせていただきます。この犯罪について、私は政治的に無実の人がいたなどとは信じておりません。無実の犠牲者に対する私の同情は無限です。それはこの同情の対象が九月一一日にアメリカで亡くなった人々だけにとどまらないからです。それが、ホワイトハウスのスローガンによって先日来「無限の正義」(infinite justice, grenzenlose
Gerechtigkeit)と呼ばれているものに関しての私の解釈です。つまり、途方もない規模で、この上もなく恐ろしい代価を払うこととなった時であろうと、自己自身の過誤、自己自身の政治的悪弊から逃れようとしない、ということです。
(『フィシュ』)
九・一一は、現代社会において、人々に赦しや責任の問題を直面させる。それはJDも例外ではない。JDはアパルトヘイト以後の南アフリカを例に、『世紀と赦し』において、赦しを論じる。赦しには言語による証言が必須である。赦しえぬものを赦すというアポリアがそこにはある。この赦しはヘーゲル的な赦しと和解の弁証法が歴史を発展させるという線形的なものではなく、非線形である。無条件的な赦しは、無条件的な歓待と同様、困難である。赦しの議論は歓待とほぼ同じ過程を辿る。赦しは個人的な感情にとどまらず、宗教、民族、国家などに政治的に利用されるが、この政治の場は不可欠である。条件的な赦しは無条件的な赦しと不可分だからである。九・一一以降、世界はこの赦しのアポリアに苦闘している。JDはこうすれば赦しが可能だなどとは口にしない。「この犯罪において、政治的に無実の人は誰もいないと思う」(『フィシュ』)から、共に悩み、考える。今日の問題の多くは非線形にさらされているのであり、JDはそれを至るところで喚起させ、非線形を思慮に入れて、新たな考察を続けようと応えている。
知と真実の彼方で人が崩壊の原理に対してそうだ(oui)と言うことができるであろう時、まさしく一つの空白の場所が残されるであろう。
(『この狂った<真実>−友愛という正しき名』)
“D’ailleurs, Derrida”には、JDの読者にとって、既知の光景も、未知のも描かれている。ただ、このJDもいつもの姿とも違うかもしれない。少年時代のJDは、ヘンリー・キッシンジャーと同様、サッカーが好きだったことは触れられていない。JDは哲学のヨハン・クライフのようだ。地中海と太平洋、フランスとアメリカ、アルジェリアとスペイン、ユダヤとアラブ、母と子、男と女、人間と他の生物、言葉と映像、ドキュメンタリーとフィクションなどに関して喋りまくるJDが印象に残る。どこかではなく、どこでもJDの方法論は機能する。この映画は”De partout, Derrida”と呼ぶべきだろう。
To lead a better life, I need
my love to be here.
Here, making each day of the
year,
Changing my life with a wave of
her hand.
Nobody can deny that there’s
something there.
There, running my hands through
her hair,
Both of us thinking how good it
can be.
Someone in speaking but she
doesn’t know he’s there.
I want her everywhere, and if
she’s beside me I know I need never care,
But to love her is to meet her
everywhere,
Knowing that my love is to
share,
Each one believing that love
never dies,
Watching her eyes and hoping
I’m always there.
To be there and everywhere,
Here, there and everywhere.
(The Beatles “Here, There And
Everywhere”)
いつからそこにいなくなったのかわからないままに、見られ続けていないと気がついたときには、決して交わらなかった視線として見た後に見ていたと認識する。それは現前と不在、すなわち見えるものと見えないものの境界に現われるハムレットの父親のような亡霊である。いるともいないとも言えない。不意にどこかへ行ってしまい、どこかに回帰する一つのメタモルフォーゼであり、自己矛盾しながら、混乱させつつ、聞く人に語りかける不気味なものである。JDは、『マルクスの亡霊たち』において、そう語っていたかどうかはわからない。だから、Jacques DerridaはJDと呼ばれるのにふさわしい。それはJe Déconstruisの頭文字にほかならない。
一つの問いが設定される以前に既に応答している、自律性を持たない、<誰が>=主体のどんな可能な自律性よりも以前に、それを目指して応答することのできるあの<oui,oui>の経験のうちに、問いを書き込み直す。
(『<正しく食べなくてはならない>あるいは主体の計算』)
D’accord, Derrida?
I’m in love with a bossanova,
He’s the one with the cash n’
over
I’m in love with his heart of
steel
I’m in love
How come no one ever told me
who I’m working for?
Down among the rich men baby,
end of war.
Here comes love forever
And it’s here comes love for no
one
Here comes love for Marilyn
And it’s all my baby, all my
baby, what are you gonna do?
In the reason in the rain
Still support the revolution
I want it, I want it, I want
that too,
But baby, but baby, it’s up to
you
To find out something that you
need to do, because…
I’m in love with Jacques
Derrida,
Read a page and I know I don’t
need to,
Take apart my baby’s heart.
I’m in love
Repeat above 4 lines only,
To err is to be human, to
forgive is to divine,
I was like an industry,
depressed and in decline.
I’m in love with bop she date
Out
I’m in love with just getting
away
I’m in love
Oh, I’m in love with a
militanté
Reach you, need you redvanté
I’m in love with a heart of
steel
I’m in love
He held it like cigarette
behind a squaddies back
He held it so it hit his leg,
so he hit his leg, oh!
And it seemed so very sad
alnight.
Well I want better than you can
give
But then I’ll tale whatever
you’ve got
‘Cos I’m a friend in time with
a kind of means
That can overthrow the lot
I said rapatious, rapatious
You can never say she ain’t,
Ain’t what?
Desire so various
I wanted to eat your nation’s
stake!
I got the sinner that you can’t
handle
I got the needs you can’t
persuade
I got the demands you can’t
meet and stand on your feet
I want more than your living
wage.
(Scritti Politti “Jacques Derrida”)
〈了〉